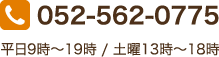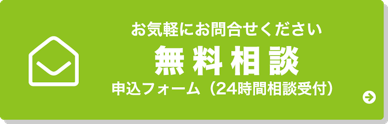遺産を分けた後に、把握していなかった債権者から内容証明郵便が届きました。どうすればよいですか。
原則として法定単純承認事由に該当し、相続放棄はできませんが、相続人の個別事情によっては認められる余地があります。
この点について、平成14年1月16日東京高等裁判所決定は、民法915条1項所定の熟慮期間について、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて相続の開始を知ったといえるので、その時点から起算すべきである旨の抗告人らの主張に対し、相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当であるとした上、遅くとも、抗告人らが相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から熟慮期間を起算すべきであり」と判示しています。
この判例によれば、遺産を分けた日(遺産分割の日)が3か月の起算点となりますので、相続放棄の申述は、その時点から3か月以内に行う必要があります。
しかし、被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との遺産分割協議内容の如何によっては相続放棄が認められる余地があります。
この点について、平成10年2月9日大阪高等裁判所決定は、次のとおり判示しています。
「もっとも、抗告人らは、他の共同相続人との間で本件遺産分割協議をしており、右協議は、抗告人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産にして有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法廷単純承認理由に該当するというべきである。しかし、抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、Bら他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。そして、仮にそのような事実が肯定できるとすれば、本件熟慮期間は、抗告人が被相続人の死亡を知った平成九年四月三〇日ではなく、国民金融公庫の請求を受けた平成九年九月二九日ころから、これを起算するのが相当というべきである。
そうすると、本件申述を受理すべきか否かは、前記相続債務の有無及び金額、右相続債務についての抗告人らの認識、本件遺産分割協議の際の相続人の話合の内容等の諸般の事情につき、更に事実調査を遂げた上で判断すべきところ、このような調査をすることなく、法定単純承認事由があるとして本件申述を却下した原審判には、尽くすべき審理を尽くさなかった違法があるといわなければならない。なお、申述受理の審判は、基本的には公証行為であり、審判手続で申述が却下されると、相続人は訟手続で申述が有効であることを主張できないから、その実質的要件について審理判断する際には、これを一応裏付ける程度の資料があれば足りるものと解される。」